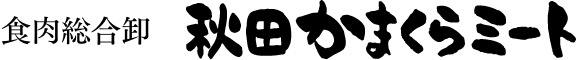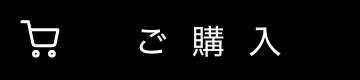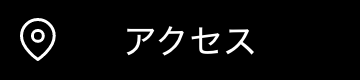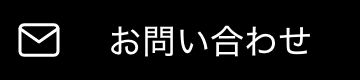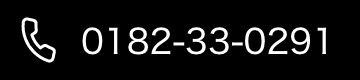どうモー、うしコラムです。
3月になり、卒業式なども済んで、まもなく入学式など新しいことが始まるシーズンがやってきます。
この季節と言えば、やっぱり桜!
今回は桜にちなんだお話です。

☝実際にこんな状況を見たらビックリでしょうね…
桜の樹の下には(牛の)死体!?
のっけから物騒な話題ですが、これは梶井基次郎の小説『桜の樹の下には』の有名な一節。
実はその牛版とも言うべき伝承があるのはご存じでしょうか?
今を遡ること800年、源氏と奥州藤原氏が戦った文治の役でのこと。源頼朝軍が行軍の際、今の山形県蔵王の地で、荷を引いていた大きな牛が力尽きて死んでしまった。兵士たちは適当なところまで運んで葬ろうとしたが、重くて運べなかったので、その場に穴を掘り、そこに牛を転がしこんで埋め、桜の樹を墓標にした。
のちにこの桜は大樹となり、牛をひっくり返して埋めた故事にちなんで寝返し桜と呼んだのですが、その言葉が「寝返り(裏切り)」に通じると不吉に思われ、いつしか「根返し桜」と呼ぶようになった…というお話。
蔵王町指定天然記念物として親しまれていましたが、2015年に根元から倒れてしまい、今は切り株と後継樹が残っているそうです。
秋田の桜
秋田を代表する桜の名所のひとつが千秋公園。ここは1603年初代藩主佐竹義宣が久保田城を築いた所で、今も城跡が公園として残っています。約650本の桜が一斉に咲き誇る様子はまさに圧巻!平成2年には公益財団法人日本さくらの会から「さくら名所100選」に選定されています。
今年(2025年)の開花予測は4月15日だそうです。
2つ目のおすすめスポットは、角館の武家屋敷通り。ここでは、樹齢300年を超える枝垂れ桜が優雅に枝を垂れ、武家屋敷の落ち着いた風景と調和した美しさがあります。
この桜は佐竹北家に公家の姫が輿入れする際、嫁入り道具のひとつにあった苗木が始まりとされ、秋田にいながら京都の風情も感じながら春のひとときを満喫できるスポットです。
3つ目のおススメスポットは、「桧木内川堤のソメイヨシノ」。
角館を流れる桧木内川沿いに約2キロメートル続く桜並木は、これも日本さくら名所100選に選ばれた絶景スポット。川沿いをのんびり散歩しながら、お花見を楽しむのも素敵な時間ですね!
秋田の桜は4月下旬が満開です。今年は秋田に来て、一味違った桜の楽しみ方にトライしてみるのはいかがでしょうか?(^^)/